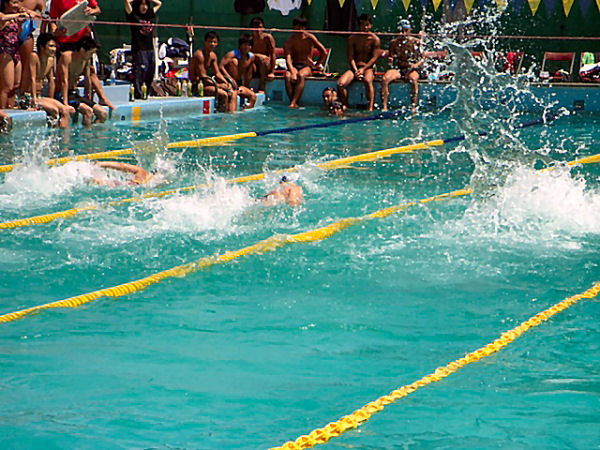ソフトテニス部(旧軟式テニス部)では、平成29年11月23日(木)に大学構内の松本楼にて、桜球会創立50周年記念式典を開催しました。
桜球会は、学習院大学・短期大学・女子大学の卒業生で、卒業時にソフトテニス部に在籍した会員で構成され、会員の親睦とソフトテニス部を援助することを目的としています。式典は、来賓として現部長の神戸先生(経済学部)や前部長の片瀬先生(理学部)をお招きし、卒業生46名と現役29名の参加を得て盛大に開催しました。最高齢は82歳の先輩で、改めて我が部の歴史と伝統の深さに触れることができました。現役時代を熱く思い出す先輩達からは近年良い戦績の現役部員に対して、心のこもった激励の言葉がかけられていました。式典は全員での院歌とエールにて終了となりましたが、近い内に再び開催して欲しいとの先輩命を受けました。今回ご都合で参加出来なかった皆様、その時は宜しくお願いします。
学習院大学 ソフトテニス部
桜球会 会長 高木利一