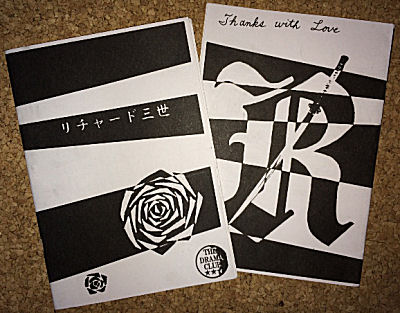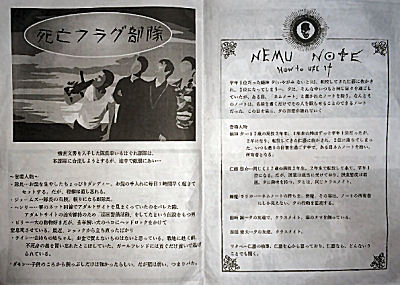平成28年5月14日(土)、学習院放送研究部OBOG会「春秋会」の第6回総会・講演会・懇親会が学習院目白キャンパス内「目白倶楽部」において開催されました。昭和32年卒業から平成10年卒業まで総勢52名が参加致しました。
総会は、定刻午後12時に開始。昭和33年卒業の山本時雄会長が議長に選出され、挨拶の後、平成27年度の活動報告、会計報告、平成28年度の活動計画を発表、審議の末賛成多数で承認されました。
総会の後、昭和43年学習院大学文学部仏文科ご卒業で、元TBSアナウンサー、現在、気象予報士会顧問、「白山朗読の会」を主宰されている石井和子氏から「今、日本語を考える」と題してご講演を頂きました。
引続き行われた懇親会では、冒頭、桜友会副会長 鈴木征様からご挨拶を頂いた後、昭和40年卒の高橋義毅副会長の乾杯のご発声で始まり、世代を超えて懇親を図り和気藹々としたなか楽しい時間が流れていきました。今回も昨年同様放送研究部現役の学生にゲストとして参加いただき、現状報告を聞くことができ大変有意義な会になりました。これで現役とOBOGとのパイプも繋がり春秋会の更なる発展が期待されるところであります。昭和41年卒の高橋勝彦副会長の閉会の辞のあと最後に全員で記念写真を撮り、来年の再会(5/13開催予定)を約して午後2時30分お開きとなりました。
尚、当日皆さまからの熊本地震に対する義捐金20,500円は、日本赤十字社を通じてお送りさせて頂きました。


講演:石井和子氏